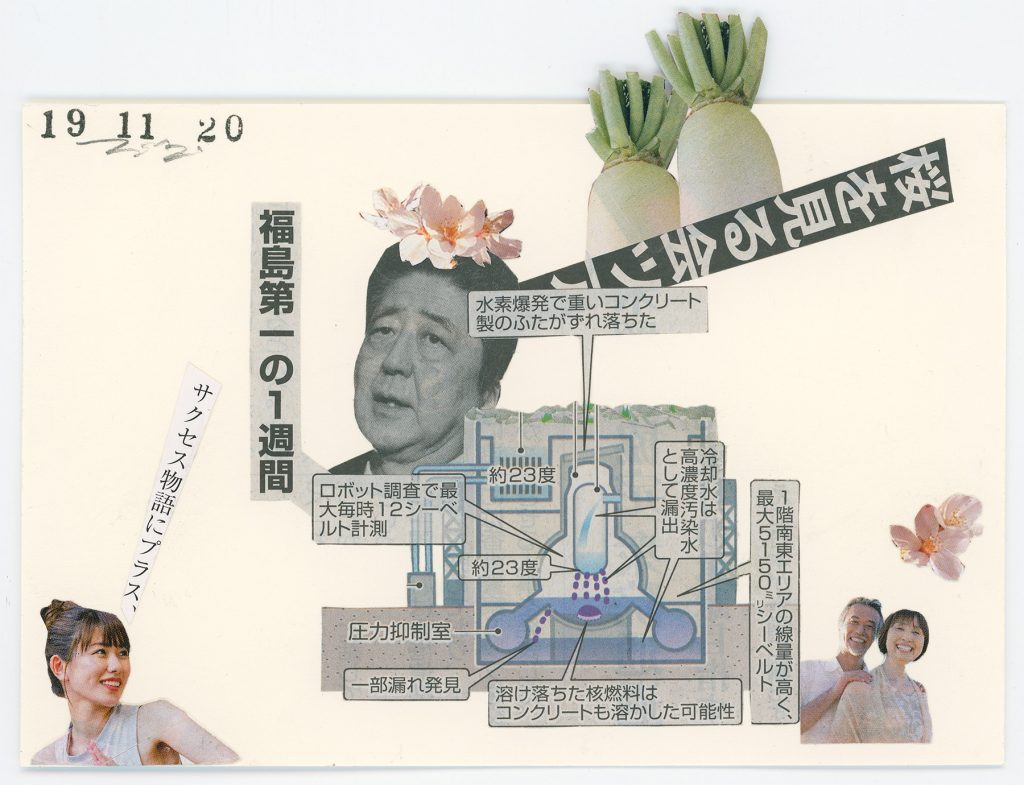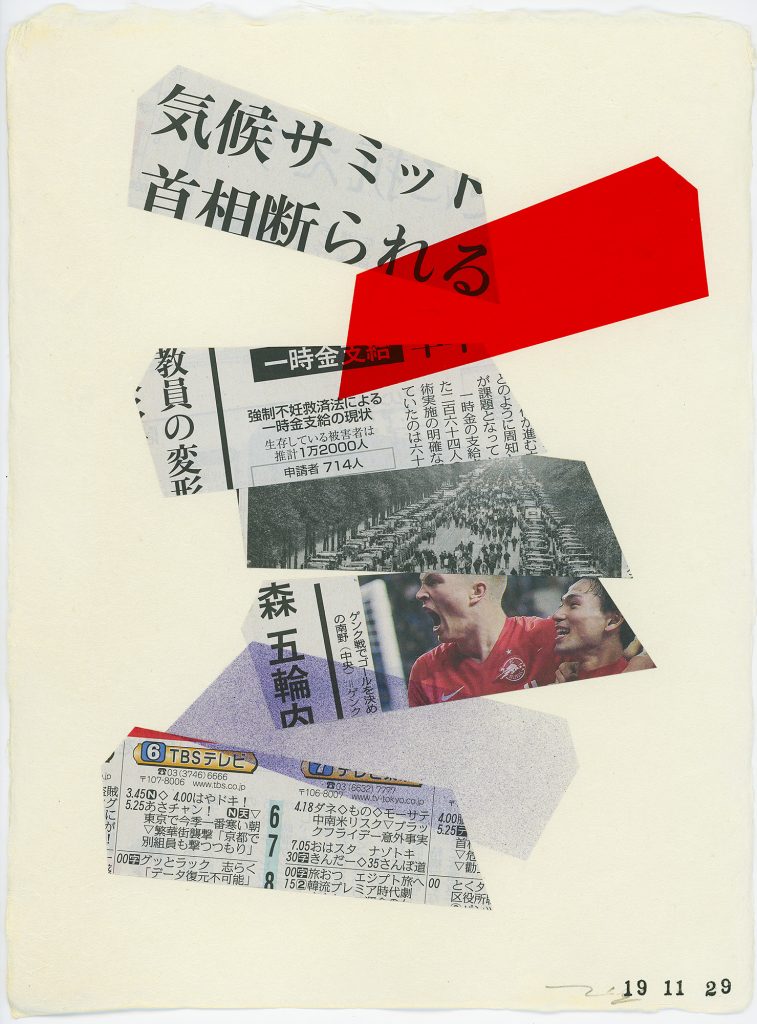千人針の五銭硬貨 / 5 sen coin sewed on a Sen-nin Bari (bellyband with 1000 stitches)
千人針に縫い付けられた5銭硬貨、「死線(シセン)をこえる」の意。このほか兵士を守るとされる女性の陰毛を縫い込んだ千人針や、戦場で渇きに苦しんだとき口に含んでその場を凌ぐため、梅酢に漬け込まれた千人針のオーラル・ヒストリーがある。 おおむね日露戦争くらいまで記録をさかのぼることのできる千人針習俗は、初期においては当局から非難される秘められた営みだったのが(千人針の祈りは最初期には徴兵忌避、その後「無事に帰還すること」に変容した。太平洋戦争後期の総力戦体制下ではひるがえって、〈銃後〉の結束を高めるため国家が推奨する活動となり、国防婦人会などを通して大量生産されるようになる。 ミクロ・レベルのナラティヴ/小さな祈り・善意/極小のマイクロモニュメントと、マクロ・レベルのナラティヴ/倫理規範/大規模モニュメントはいつでも対置されるわけではなく、連続するグラデーションの中に分かちがたく点在する。