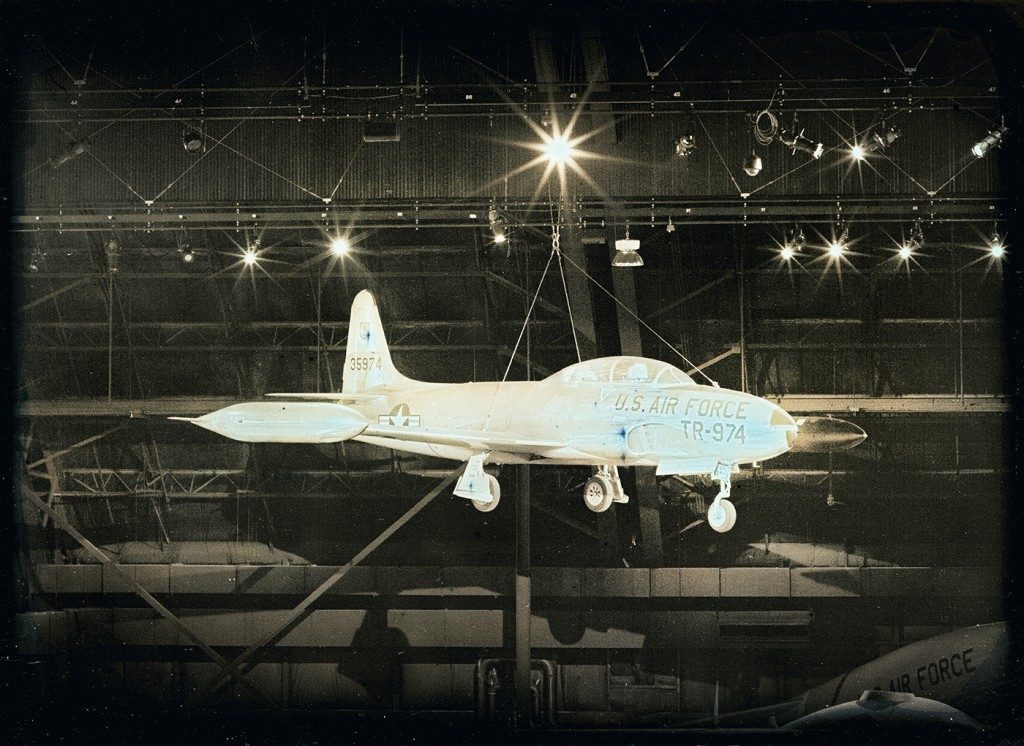Renewal Notice
Thank you for visiting! Takashi Arai Studio is temporary in the process of renewal. The new site will be relaunched by June, 2017. 訪問ありがとうございます。本サイトはただいまリニューアル作業中です。2017年6月までには作業完了予定ですので、ぜひまたお立ち寄りください。 “Takashi Arai: Cent soleils” Galerie Camera Obscura/パリ写真月間 2017 2017年4月4日 – 5月27日 “Photobook Phenomenon” Centre de Cultura Contemporània, バルセロナ 2017年3月17日-8月27日 “THE POWER OF IMAGES: MAST Collection. An iconic selection of photographs on industry and work” MAST, Bologna May 3 - Sep 24, 2017 –『ナショナルジオグラフィック日本版』3月号・特集 –『現代詩手帖』シリーズ・エッセイ「陽の光あるうちに」(1年間の表紙作品/散文連載) –『図書』1-3月号 「新しいモニュメントの到来のために」(全3回連載)全国書店で無料配布中 – Web版『水牛のように』連載中